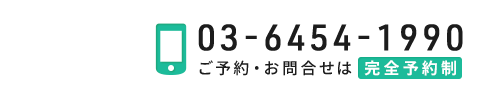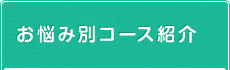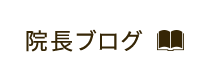ケガをしたり、熱いものに触れたりした時、強い圧力を感じたり、体内に炎症が起こっている時など、私たちの身体は「刺激」を感じます。この「刺激」が電気信号となって、神経を通じて脳に伝わると、私たちは「痛み」を感じます。
「痛み」の感じ方には個人差があり、精神的ストレスにさらされると脳の機能が低下し、ストレスがない時と比べると「痛み」をより強く感じることがわかっています。
痛みは、どういう仕組みで出てくるのか? そのメカニズムについてご説明したいと思います。
痛みは誰でも経験する感覚です。苦しく、辛く、嫌な感覚であり、出来れば経験したくない感覚です。
痛みは、自分の身体が傷害されるときに感じる感覚ですので、自分の身体を傷害しないように、行動を自制させることになります。傷害により嫌な感覚(痛み)を感じることになるので、傷害しない、傷害させない行動をとるようになるのです。
先天性無痛無汗症という、痛みを感じない先天性疾患の場合、痛みを感じないため、どのような行動でも恐れを感じなく出来るそうです。その結果として、下肢を中心に骨折・脱臼・骨壊死などが多発し、虫歯の悪化が進むなど、体に障害を起します。また、「他人が痛みを感じる」ということが理解できないため、社会生活が難しくなってきます。
このように、痛みは自分が生きていくこと、人間が共存していくうえで、とても大切な感覚なのです。
痛みの種類
「痛み」は医学用語で「疼痛」と言います。疼痛は大きく分けて3種類に分けることができます。順に説明いたします。
1.侵害受容性疼痛
骨折や打撲、切り傷、やけどなどのケガにより傷害された部分に発生した痛みのことです。
この痛みの特徴としては、ケガをした部分にプロスタグランジンやブラジキニンなどの痛みを出してしまう物質の発現が見られ、この物質が末梢神経にある「侵害受容器」を刺激することで痛みを感じます。この仕組みから、この痛みは「侵害受容性疼痛」と呼ばれています。
末梢の侵害受容器が、外的な刺激によって活性化されて生じるもので、重くズーンとした痛み方が特徴で、頭痛、歯痛、関節通、などもこれに含まれます。
対処法としては、ほとんどの場合が急性に生じた痛みのため、一般的には鎮痛薬の効果があります。急性の打撲や捻挫は冷やすのが効果的で、慢性の腰痛などは、温めるのが痛みを抑える効果があります。このように侵害受容性疼痛は痛みの時期によって、適切な対処が変わってきます。
2.神経障害性疼痛
何らかの原因により神経が障害され、それによっておこる痛みのことを言います。
具体的には、帯状疱疹が治った後の長引く痛み、糖尿病の合併症に伴う痛み、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症による坐骨神経痛などです。
侵害受容性疼痛のように傷や炎症など明確な原因が見えないにもかかわらず痛みがある場合には、神経が原因となっていることがあります。40代以上に多く、日本では約660万人以上の患者さんがいると推定されています。
対処法としては、理学療法や手術で神経の絞扼(しめつけ)などの障害を改善する。神経に対して効果のある鎮痛薬を服用するなどの方法があります。また、温めることによって痛みの緩和を期待することもできます。
3.心因性疼痛
この痛みは、仕事や日常生活の中において、慢性的もしくは強いストレスを蓄積することで生じる身体の痛みをいいます。
不安やイライラなどの心理状態が、無意識下でこれらと向き合うことを避けるために身体の特定部位に虚血状態(血流の滞り)を発生させ、痛みを引き起こすとされています。天気や季節による痛みも心因性疼痛にあたるとされます。
心因性疼痛はおもに、自律神経やホルモンバランス、免疫系に不調をきたすことで痛みが生じます。この痛みや不快感によって、それがさらにストレスを引き起こし、抑うつ(うつ病)となるケースも少なくありません。
対処法としては、鎮痛剤の服用の他、ストレス要因の排除・マッサージなどで虚血状態を改善するなど、心理的な部分の根本解決と、虚血状態を改善する対処療法の併用が必要です。
痛みを上手に伝える方法
病気やケガをしてしまった時、日本語には「痛み」を伝える言葉がたくさんあります。
症状が伝わりやすい、日本語の「痛み」の表現をご紹介します。
- びりびり:しびれたような感覚があるとき
- じんじん:しみるような痛みがあるとき
- ちくちく:針で刺すような痛みがあるとき
- ひりひり:焼けるような痛みが続くとき
- きりきり:締めつられるような痛みがあるとき
- ずきずき:頭や歯が痛いとき
痛みの種類に合った言葉を使うことで、痛みの原因や、どのくらい痛いかを、他の人に伝えやすくなります。
次は体の部位によって分類します。
頭
「頭が痛い」ときには、このような言葉を使います。
- 頭がズキズキする:こめかみ(目の真横、耳の真上)あたりが締めつけられるように痛いとき。
- 頭がガンガンする:頭全体が痛いとき。
- 頭がぼーっとする:熱があるなどして、ぼんやりするとき。
首
「首が痛い」ときには、このような言葉を使います。
- 首がガチガチになっている、首がバキバキになっている:首の筋肉が固まって重いとき。
背中・腰
「背中や腰が痛い」ときには、このような言葉を使います。
- 背中(腰)がピキッとする:一瞬だけ、電気が走ったような痛みがあるとき。
- 背中(腰)がズーンとする:痛みが長く続いているとき。
お腹
「お腹が痛い」ときには、このような言葉を使います。
- お腹がキリキリする、お腹がシクシクする:胃のあたりが締めつけられるような痛みのとき
- お腹がチクチクする:針で刺すような痛みがあるとき
腕・手
「腕や手が痛い」ときには、このような言葉を使います。
- 腕(手)がビリビリする:しびれたような感覚があるとき
- 腕(手)がジンジンする:焼けるような痛みがあるとき
- 腕(手)がチクチクする:針で刺すような痛みがあるとき
足
「足が痛い」ときには、このような言葉を使います。
- 足がビリビリする:しびれたような感覚があるとき
- 足がジンジンする:焼けるような痛みがあるとき
- 足がチクチクする:針で刺すような痛みがあるとき
- 足がパンパンになる:歩きすぎて足が張っているとき
痛みの強さを伝える方法
痛みは感覚のものなので、どのくらい痛みがあるのかはなかなか伝わりにくいものです。通常の場合、眠っている時は痛みを感じていませんが、痛くて眠ることができない。といった場合があります。何もしていない状態(安静時)でも痛みがある場合は、痛みのレベルが高い状態ですので、出来るだけ早く病院に行きましょう。
痛みの強さを数字で表す方法があります。ペインスケールと呼ばれるものですが、一般的には「最も痛い状態を10にすると、今はいくつくらいですか?」といった表し方になります。
その他としては、つぎのような事がポイントになります。
- 痛めた原因
- 痛い場所
- どんなときに痛いか
- 痛みがどのくらいの時間続いているか
- どうすると痛みが減るのか
例)昨日の朝、工事現場で重い鉄骨を持ち上げたときに、急に腰のここ(←痛い場所を指でさして)が痛くなりました。
歩けないくらい痛くて、立っているときも、座っているときも痛いです。
横になると痛みが楽になりますが、立ち上がる動作が辛いです。
昨日の痛みを10とすると今は少し良くなって7くらいです。
このような感じだと、伝わりやすいですね。
痛みの状態を正確に伝えるのは、少し難しいかもしれません。
痛みは我慢していると、悪い症状をイメージしがちです。長く苦しむことなく、早めに専門機関に相談するようにしましょう。
病院や整体・整骨院に行ったときなどの説明・表現の仕方の参考になればうれしいです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。